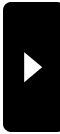› 伊万里市 二里コミュニティセンター › 歴史の散歩道
› 伊万里市 二里コミュニティセンター › 歴史の散歩道2021年10月12日
2021 白露 神乃原八幡宮大祭神事
かみのはらはちまんぐうたいさいのしんじ
神之原八幡宮大祭の神事
大里区の神之原八幡宮大祭の神事が執り行われました。コロナの影響で大変残念ながら神事のみとの事、無病息災、五穀豊穣などを祈願されました。
9月15日 大里区


神之原八幡宮大祭の神事
大里区の神之原八幡宮大祭の神事が執り行われました。コロナの影響で大変残念ながら神事のみとの事、無病息災、五穀豊穣などを祈願されました。
9月15日 大里区
2021年09月03日
2021 処暑 千畳敷からの景観
ちそかいせいとこしだけそうどう
地租改正と腰岳騒動
地租改正
明治新政府は、明治六年(1873年)七月、地租改正法を発布しました。
地租改正法がこれまでと違う点は、①従来のように土地の収穫を標準として賦課するものではなく、土地の価格に応じて課税する。②物納に代わって金納とする。③地租は毎年地価の百分の三(明治一〇年百分の二・五に改正)を定率として課し豊凶に左右されない。④納税者は農地の所有者である。というものでした。地価の決定、金納制の採用、所有権の確定は何れも大問題で、中でも所有権の確定は最も大きな問題を含んでいて、小作農民が所有権の確定をめぐって抗争を繰り返し、腰岳騒動(地騒動とも表現)に代表される、様々な争いに発展したのでした。
この腰岳騒動は西松浦郡誌につぎのように記されています。
「明治一三年前後地租改正時代に有田郷数村の農民群をなし腰岳に蝟集(いしゅう)し事頗る(すこぶる)不穏、先是小作条件等に付…訴願するところありしが終に此一揆を起こすに至りしなり…郡長永田暉明斡旋調停に没頭し事鎮静に帰したり」これがいわゆる腰岳騒動であります。
(二里町誌(H25年3月)より抜粋)
8月31日千畳敷より腰岳を望む

腰岳展望台より伊万里市街を望む

地租改正と腰岳騒動
地租改正
明治新政府は、明治六年(1873年)七月、地租改正法を発布しました。
地租改正法がこれまでと違う点は、①従来のように土地の収穫を標準として賦課するものではなく、土地の価格に応じて課税する。②物納に代わって金納とする。③地租は毎年地価の百分の三(明治一〇年百分の二・五に改正)を定率として課し豊凶に左右されない。④納税者は農地の所有者である。というものでした。地価の決定、金納制の採用、所有権の確定は何れも大問題で、中でも所有権の確定は最も大きな問題を含んでいて、小作農民が所有権の確定をめぐって抗争を繰り返し、腰岳騒動(地騒動とも表現)に代表される、様々な争いに発展したのでした。
この腰岳騒動は西松浦郡誌につぎのように記されています。
「明治一三年前後地租改正時代に有田郷数村の農民群をなし腰岳に蝟集(いしゅう)し事頗る(すこぶる)不穏、先是小作条件等に付…訴願するところありしが終に此一揆を起こすに至りしなり…郡長永田暉明斡旋調停に没頭し事鎮静に帰したり」これがいわゆる腰岳騒動であります。
(二里町誌(H25年3月)より抜粋)
8月31日千畳敷より腰岳を望む
腰岳展望台より伊万里市街を望む
2021年08月23日
2021 処暑 かつて二里中学校がありました
にりちゅうがっこうあとち
二里中学校跡地
二里中学校は、昭和二十二年四月(1947年)二里村立中学校として開校されました。当初は二里小学校に併設のされていた青年学校の校舎が使用されていましたが、昭和三十一年(1956年)校舎建設が完了しました。当時の二里中学校の面影を残したものは、ほとんど無くなっていますが、通学路から校舎へ入る正門だけが、当時のまま残っています。
昭和三十三年(1958年)二里中学校と東山代中学校が統合し、国見中学校が開校されました。二里中学校は、昭和三十三年三月卒業の第十一回生までの十一年間で1,277名と多くの生徒が巣立っています。
二里中学校の近くに鎮座(ちんざ)されていた『大黒(だいこく)さん』は、有田川改修工事によって鎮座されている場所は変わっていますが、今も昔もふくよかな顔で、毎日子供達の通学の安全を見守っています。
(ふたさとまるごと博物館Ⅲ(H22.10.10)より抜粋)
8月20日(二里小学校)

(大黒さん)

二里中学校跡地
二里中学校は、昭和二十二年四月(1947年)二里村立中学校として開校されました。当初は二里小学校に併設のされていた青年学校の校舎が使用されていましたが、昭和三十一年(1956年)校舎建設が完了しました。当時の二里中学校の面影を残したものは、ほとんど無くなっていますが、通学路から校舎へ入る正門だけが、当時のまま残っています。
昭和三十三年(1958年)二里中学校と東山代中学校が統合し、国見中学校が開校されました。二里中学校は、昭和三十三年三月卒業の第十一回生までの十一年間で1,277名と多くの生徒が巣立っています。
二里中学校の近くに鎮座(ちんざ)されていた『大黒(だいこく)さん』は、有田川改修工事によって鎮座されている場所は変わっていますが、今も昔もふくよかな顔で、毎日子供達の通学の安全を見守っています。
(ふたさとまるごと博物館Ⅲ(H22.10.10)より抜粋)
8月20日(二里小学校)
(大黒さん)
2021年04月28日
2021 穀雨 炭山の水源
いちのがわぶんすいぜき
一ノ川分水堰
吉野川上流の一ノ川と、国見県道が立体交差する国見一号橋のすぐ下方に県(伊万里農林事務所)が建設した砂防堰提があって、その下方にこの分水堰があります。二里町最小の井堰ともいえるもので、炭山では「一ノ井手」とも呼んでいます。この分水堰は大正七年(1918)の刻印があり花崗岩(御影石)製のものですが、分水慣行は藩政時代と伝えられますので、改修前の材質は砂岩製だった可能性が考えられます。現在でも「ふうつ」(水番)によって、分水率がきびしく監視されており、慣行水利権の強大さを今に伝えています。
この分水堰の構造は下流に向かって右20cm、左48cmの切込みがあり、その分水率は、右(川内)三割、左(中田)七割となっていて、川内三割の水は一ノ川に落ちて、吉野川水系のかんがい用水を賄い、中田七割の水はU字溝で約25ヘクタールの水田用水に利用されています。
(二里町誌 H25年3月より抜粋)
4月26日(分水堰 上流を望む)

(分水堰 下流を望む。)

一ノ川分水堰
吉野川上流の一ノ川と、国見県道が立体交差する国見一号橋のすぐ下方に県(伊万里農林事務所)が建設した砂防堰提があって、その下方にこの分水堰があります。二里町最小の井堰ともいえるもので、炭山では「一ノ井手」とも呼んでいます。この分水堰は大正七年(1918)の刻印があり花崗岩(御影石)製のものですが、分水慣行は藩政時代と伝えられますので、改修前の材質は砂岩製だった可能性が考えられます。現在でも「ふうつ」(水番)によって、分水率がきびしく監視されており、慣行水利権の強大さを今に伝えています。
この分水堰の構造は下流に向かって右20cm、左48cmの切込みがあり、その分水率は、右(川内)三割、左(中田)七割となっていて、川内三割の水は一ノ川に落ちて、吉野川水系のかんがい用水を賄い、中田七割の水はU字溝で約25ヘクタールの水田用水に利用されています。
(二里町誌 H25年3月より抜粋)
4月26日(分水堰 上流を望む)
(分水堰 下流を望む。)
2021年02月18日
2021 立春 東八谷搦部落誌
ひがしはちやがらみのこんじゃく
東八谷搦の今昔
一 八谷搦の自然
新田川改修以前の八谷搦は、海抜〇メートルのうえに、新田川の川幅も河口の水門も狭かったので、大雨と伊万里湾の満潮が重なると、水田はまたたく間に冠水し、大海のようになりました。時には居住地域まで水かさがあり、床下浸水も度々でした。このように、自然環境は必ずしも快適ではなかったのですが、搦に生きる人々は衆知を生かし、たゆまぬ努力で環境を克服してきました。
二 八谷搦の灌漑(かんがい)用水(江湖山溜池)
干拓地八谷搦には、どうしても水利の確保が不可欠でした。古老の話では、上下二箇所に溜池があって、下の溜池は上の溜池(江湖山溜池)の余水を貯水する構造になっていて、下の堤は市道川東・富士町線の道路敷その他に利用されて、現在は消滅しているようです。この溜池の利用は、日照り続きで干拓地のクリークの水が底をついた時、渚川へ放水し、新田川を経て干拓地に送りこまれる仕組みになっています。
(二里町誌(H25.3.)より抜粋)
2月12日(新田川河口)

(江湖山溜池)

東八谷搦の今昔
一 八谷搦の自然
新田川改修以前の八谷搦は、海抜〇メートルのうえに、新田川の川幅も河口の水門も狭かったので、大雨と伊万里湾の満潮が重なると、水田はまたたく間に冠水し、大海のようになりました。時には居住地域まで水かさがあり、床下浸水も度々でした。このように、自然環境は必ずしも快適ではなかったのですが、搦に生きる人々は衆知を生かし、たゆまぬ努力で環境を克服してきました。
二 八谷搦の灌漑(かんがい)用水(江湖山溜池)
干拓地八谷搦には、どうしても水利の確保が不可欠でした。古老の話では、上下二箇所に溜池があって、下の溜池は上の溜池(江湖山溜池)の余水を貯水する構造になっていて、下の堤は市道川東・富士町線の道路敷その他に利用されて、現在は消滅しているようです。この溜池の利用は、日照り続きで干拓地のクリークの水が底をついた時、渚川へ放水し、新田川を経て干拓地に送りこまれる仕組みになっています。
(二里町誌(H25.3.)より抜粋)
2月12日(新田川河口)
(江湖山溜池)
2021年02月09日
2021 立春 大里部落誌
おおざと しゅうらくのおこり
大里 集落の起こり
村や集落の形成の歴史を知る有力な資料の一つに鍋島藩の郷村帳があります。貞享四年(1687年)の郷村帳に、中字、小字程度の集落名が次のように記されています。
一、大里村 香子 本村上下 風堂 丹花 福母 石堂 浜 川東 江湖
この大里村とは現在の大字のことで川東、福母を含んだ広い範囲を言うが、本村上下・風堂・丹花・石堂・浜が現在の大里集落です。
・特徴的な私称地名
①字中山にある「神の木(かんのき)」
熊野社の神殿横にあった大松(昭和一七年台風で倒木、
樹齢八〇〇~一〇〇〇年と推定)の愛称の「神の木」が移動
して定着したもの。
②字大木戸にある「木戸」・「修路(しゅうじ)」
有田郷「郷蔵」の入口付近を「棚門(きと)」と呼んでいた。
「修路」は家と家との間の小道、路地のこと。
③大里川の「テーノ川」・「チーデー」(築土居)
大里川の一部分を「テーノ川」というのは、牧瀬精米所裏の
「樋の川(といのかわ)」のこと。又川と大里川の合流点を
「チーデー」というのは「築土居(つくどい)」のこと。
④字古屋田にある「ソーベシ」
「横たわる(動詞ソベル)」の意味の「ソベ石」がなまって
「ソーベシ」となったもの。
⑤字丹花(旦過)
禅宗で修行僧が一夜の宿泊をすること、長期の修行のため訪れた
僧の入寺をすぐに認めないで数日座禅させることの二つの意味が
あり、宿泊所の旦過屋(や)か旦過寮があった名残。
⑥字北古場にある「禅門ビャート」
身寄りの判らない死体を埋葬した墓地で「火屋処(ひやと)」が
なまって「ビヤート」になったもの。
⑦字七田にある「アリタノシチタ」
字七田の「七田」については、「松浦家世伝」に伊万里氏と有田氏
の小合戦の様子が、・・・於有田志知田田原、有田兵敗走、と記録
されており、「七田」のこととされている。
(二里町誌(H25年3月)より抜粋)
2月3日 大里公民館

シジュウカラ(大里公民館にて)

神之原八幡宮

大里 集落の起こり
村や集落の形成の歴史を知る有力な資料の一つに鍋島藩の郷村帳があります。貞享四年(1687年)の郷村帳に、中字、小字程度の集落名が次のように記されています。
一、大里村 香子 本村上下 風堂 丹花 福母 石堂 浜 川東 江湖
この大里村とは現在の大字のことで川東、福母を含んだ広い範囲を言うが、本村上下・風堂・丹花・石堂・浜が現在の大里集落です。
・特徴的な私称地名
①字中山にある「神の木(かんのき)」
熊野社の神殿横にあった大松(昭和一七年台風で倒木、
樹齢八〇〇~一〇〇〇年と推定)の愛称の「神の木」が移動
して定着したもの。
②字大木戸にある「木戸」・「修路(しゅうじ)」
有田郷「郷蔵」の入口付近を「棚門(きと)」と呼んでいた。
「修路」は家と家との間の小道、路地のこと。
③大里川の「テーノ川」・「チーデー」(築土居)
大里川の一部分を「テーノ川」というのは、牧瀬精米所裏の
「樋の川(といのかわ)」のこと。又川と大里川の合流点を
「チーデー」というのは「築土居(つくどい)」のこと。
④字古屋田にある「ソーベシ」
「横たわる(動詞ソベル)」の意味の「ソベ石」がなまって
「ソーベシ」となったもの。
⑤字丹花(旦過)
禅宗で修行僧が一夜の宿泊をすること、長期の修行のため訪れた
僧の入寺をすぐに認めないで数日座禅させることの二つの意味が
あり、宿泊所の旦過屋(や)か旦過寮があった名残。
⑥字北古場にある「禅門ビャート」
身寄りの判らない死体を埋葬した墓地で「火屋処(ひやと)」が
なまって「ビヤート」になったもの。
⑦字七田にある「アリタノシチタ」
字七田の「七田」については、「松浦家世伝」に伊万里氏と有田氏
の小合戦の様子が、・・・於有田志知田田原、有田兵敗走、と記録
されており、「七田」のこととされている。
(二里町誌(H25年3月)より抜粋)
2月3日 大里公民館
シジュウカラ(大里公民館にて)
神之原八幡宮
2021年02月04日
2021 大寒 笹尾搦
ささおがらみ
笹尾搦
節分は例年2月3日ですが、今年は124年ぶりに2月2日でした。最も寒さが厳しい時期とされる大寒も過ぎ、春の足音が聞こえてくる立春です。
季節の変わり目の体調管理にも十分に気をつけたいものです。
松尾搦に続いて出来たのが笹尾搦です。田地二町歩に過ぎない小規模な搦ですが、池田万右衛門、才右衛門親子二代で、長い歳月と幾多の困難を克服して完成したものです。
万右衛門は辺古島一族の祖で、片岡家所蔵の古文書に、「元文五年庚年申(一七四〇)有田郷大里村に笹尾搦築立候事云々」の記述があります。
川東川拡張以前は、古井樋に当たるところに龍神祠があり、「元文五年庚申十二月建立 施主清左衛門」(清左衛門は二代目池田万右衛門の岳父)の銘が入っていましたが、川東川拡張により新しい八大龍王の碑が、旧碑より約二メートル上方に建てられています。
碑の側面には「施主片岡清左衛門 元文五申年十二月吉日 改修昭和六一年九月吉日」と刻まれています。
(二里町誌(平成25年3月)より抜粋)
2月2日 笹尾搦の八大龍王社

有田川土手より、新田川河口、腰岳を望む

笹尾搦
節分は例年2月3日ですが、今年は124年ぶりに2月2日でした。最も寒さが厳しい時期とされる大寒も過ぎ、春の足音が聞こえてくる立春です。
季節の変わり目の体調管理にも十分に気をつけたいものです。
松尾搦に続いて出来たのが笹尾搦です。田地二町歩に過ぎない小規模な搦ですが、池田万右衛門、才右衛門親子二代で、長い歳月と幾多の困難を克服して完成したものです。
万右衛門は辺古島一族の祖で、片岡家所蔵の古文書に、「元文五年庚年申(一七四〇)有田郷大里村に笹尾搦築立候事云々」の記述があります。
川東川拡張以前は、古井樋に当たるところに龍神祠があり、「元文五年庚申十二月建立 施主清左衛門」(清左衛門は二代目池田万右衛門の岳父)の銘が入っていましたが、川東川拡張により新しい八大龍王の碑が、旧碑より約二メートル上方に建てられています。
碑の側面には「施主片岡清左衛門 元文五申年十二月吉日 改修昭和六一年九月吉日」と刻まれています。
(二里町誌(平成25年3月)より抜粋)
2月2日 笹尾搦の八大龍王社
有田川土手より、新田川河口、腰岳を望む
2020年12月09日
2020 初冬 吉野の師走
よしののふうけい
吉野の風景
吉野神社祭礼
秋祭りは昭和一〇年頃までは十二月の第一午の日、青年団の前夜祭で始まり境内の広場で生木を燃やして、暖をとりながらしめ縄をなう未婚の若者達の勇壮なかけ声が夜のしじま*を破ったものでした。夜明け前に、若者達はしめ縄を社前の大鳥居(おおとりい)につるし、神殿に拝礼、衣服を改めて祭礼の営所の第一賓客(ひんかく)となってご馳走にあずかったものでしたが、戦後は、農地解放による小作米等の減収にともない祭礼の運営に支障があったので、一部の壮年男子を加えてしめ縄作りの前夜祭となりました。 *夜のしじま:静まり返った夜の様子
(二里町誌(H.25.3)より抜粋)
12月7日 吉野神社(吉野権現)新調されたしめ縄


鬼火炊きのやぐら

鬼火炊きのイルミネーション点灯式の案内(吉野公民館の掲示板)

吉野の風景
吉野神社祭礼
秋祭りは昭和一〇年頃までは十二月の第一午の日、青年団の前夜祭で始まり境内の広場で生木を燃やして、暖をとりながらしめ縄をなう未婚の若者達の勇壮なかけ声が夜のしじま*を破ったものでした。夜明け前に、若者達はしめ縄を社前の大鳥居(おおとりい)につるし、神殿に拝礼、衣服を改めて祭礼の営所の第一賓客(ひんかく)となってご馳走にあずかったものでしたが、戦後は、農地解放による小作米等の減収にともない祭礼の運営に支障があったので、一部の壮年男子を加えてしめ縄作りの前夜祭となりました。 *夜のしじま:静まり返った夜の様子
(二里町誌(H.25.3)より抜粋)
12月7日 吉野神社(吉野権現)新調されたしめ縄
鬼火炊きのやぐら
鬼火炊きのイルミネーション点灯式の案内(吉野公民館の掲示板)
2020年10月21日
2020 晩秋 千畳敷
せんじょうじきのあき
千畳敷の秋
白岩から北西に下って八合目から七合目の傾斜地、広さ約50ヘクタールの原野を「千畳敷」と呼んでいますが、明治・大正の頃までは共同の草刈場でした。ここは明治一三年、伊万里・有田郷の農民が、土地所有権の問題で蓆旗(むしろばた)を立てて立て籠もった「腰岳騒動」の集結地でもあります。また、大正から昭和の初期までは、二里村在郷軍人の実弾射撃場でもあり、古くから雨乞い行事として千束焚(せんばたき)が行われた場所でもあります。
(二里町誌(H.25年3月)より抜粋)
10月19日 千畳敷

千畳敷より伊万里湾を望む

千畳敷の秋
白岩から北西に下って八合目から七合目の傾斜地、広さ約50ヘクタールの原野を「千畳敷」と呼んでいますが、明治・大正の頃までは共同の草刈場でした。ここは明治一三年、伊万里・有田郷の農民が、土地所有権の問題で蓆旗(むしろばた)を立てて立て籠もった「腰岳騒動」の集結地でもあります。また、大正から昭和の初期までは、二里村在郷軍人の実弾射撃場でもあり、古くから雨乞い行事として千束焚(せんばたき)が行われた場所でもあります。
(二里町誌(H.25年3月)より抜粋)
10月19日 千畳敷
千畳敷より伊万里湾を望む
2020年09月24日
2020 仲秋 有田大膳孝広公の墓
有田大膳孝広公(紹平君坦居士)の墓
明治中期頃まで10戸程の集落があったという「上ノ原」の毘沙門堂(文殊堂ともいう)のすぐ裏手に、紹平君坦居士と陰刻した板碑がみつかりました。これは有田大膳孝広公の供養墓とされていますが、有田家系図によると、「延宝五年(1677年)一二月二三日没、五十七才、紹平君坦」となっていて、上ノ原の墓標と一致します。
唐船城は天正一八年(1590年)、廃城となりますが、神埼に移封した有田左馬助孝紀(竜造寺系二代城主)の子、有田大膳孝広(竜造寺系三代城主)の墓が唐船廃城後でもあるのに、なぜ墓碑が内ノ馬場にあるのか、記録・伝承もなく詳細は霧の中という感があります。
(二里町誌(H.25年3月)より抜粋。なお、二里町誌やふたさとまるごと博物館Ⅲは二里コミュニティセンターで購入できます。℡0955-23-3024までお問合せ下さい。)
9月23日 紹平君坦居士碑(上ノ原)

明治中期頃まで10戸程の集落があったという「上ノ原」の毘沙門堂(文殊堂ともいう)のすぐ裏手に、紹平君坦居士と陰刻した板碑がみつかりました。これは有田大膳孝広公の供養墓とされていますが、有田家系図によると、「延宝五年(1677年)一二月二三日没、五十七才、紹平君坦」となっていて、上ノ原の墓標と一致します。
唐船城は天正一八年(1590年)、廃城となりますが、神埼に移封した有田左馬助孝紀(竜造寺系二代城主)の子、有田大膳孝広(竜造寺系三代城主)の墓が唐船廃城後でもあるのに、なぜ墓碑が内ノ馬場にあるのか、記録・伝承もなく詳細は霧の中という感があります。
(二里町誌(H.25年3月)より抜粋。なお、二里町誌やふたさとまるごと博物館Ⅲは二里コミュニティセンターで購入できます。℡0955-23-3024までお問合せ下さい。)
9月23日 紹平君坦居士碑(上ノ原)